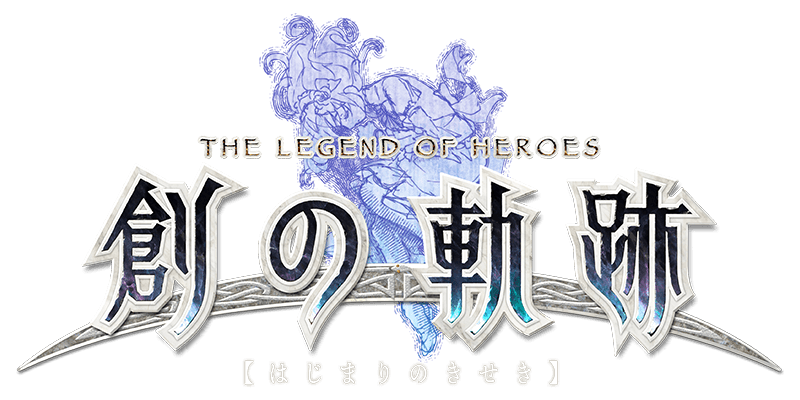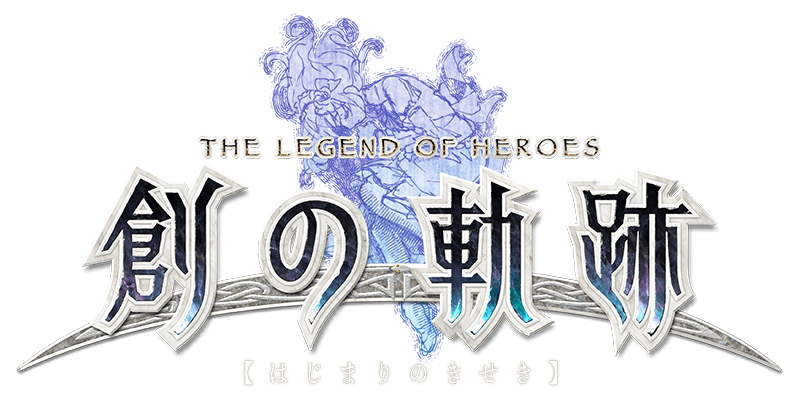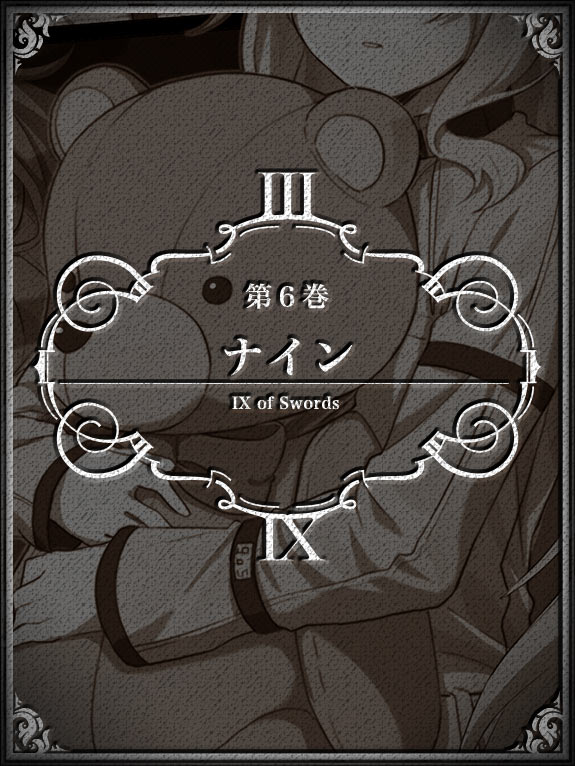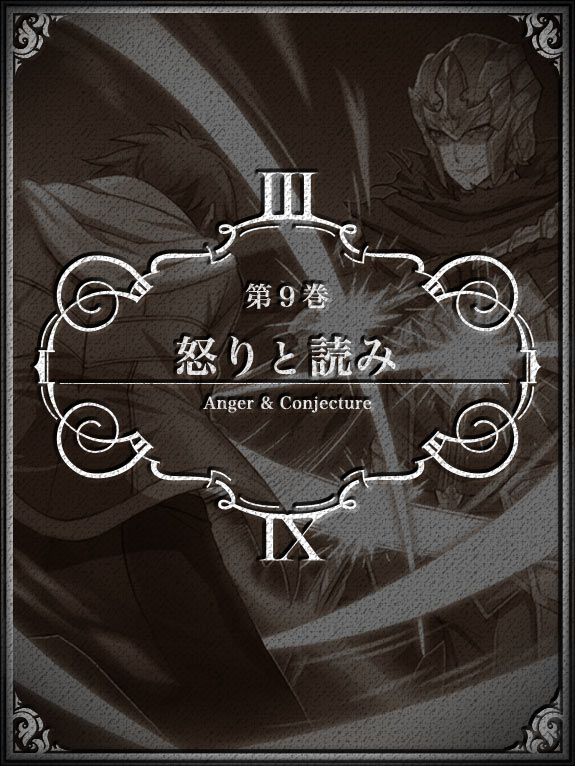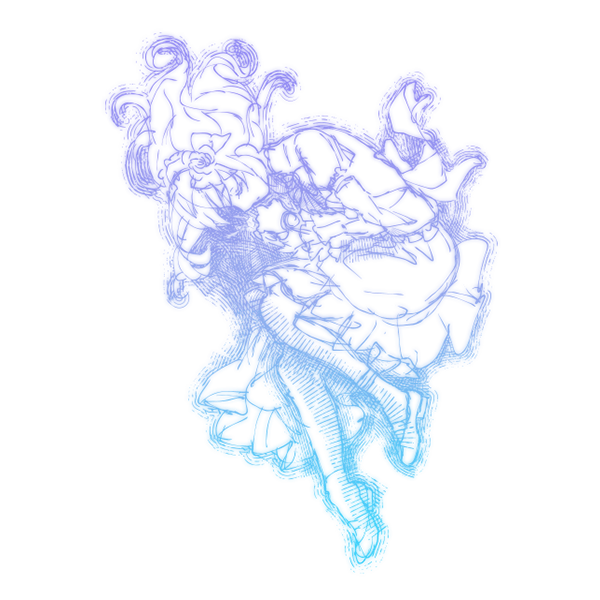レミフェリア公国、東北の港町に1隻の大きな客船が停泊している。ひと目で資産家か貴族御用達とわかるほど豪華な造りで、ぞろぞろと身なりのよい客たちが乗船していく。
そのなかで、少々目を引く二人がいた。お嬢様と執事――まさにそう呼ぶしかない装いと言動の二人。それ自体はこの場ではありふれた組み合わせだが、問題はその年齢。どちらも12、3歳にしか見えない容貌で、はっきりいって子供二人だ。
「ま、待ってくださいよぉ~ お嬢様~~」
大きな旅行カバンを引きずり、執事の少年はへとへとになりながら前を歩く少女を追いかける。身に着けている燕尾服は上質なものだが、目のほとんどが前髪に遮られ、動きにも覇気がなく、いかにも気弱そうな少年だ。
「早くしなさいこのノロマ! これ以上グズグズしたら、その無駄な脚を犬に噛み千切らせるわよ!」
辛辣な言葉を吐きながら先頭を歩くのは幼い少女。
傲慢で高圧的な態度をとっているが、その外見は実に可愛らしいもの。人形のような整った顔立ちに、サファイア色の透きとおった瞳。髪型はツインテールで、その先端はわずかにロールがかかっている。
フリル多めの、黒を基調としたドレスで身を包み、そしていちばん目立つのは、片腕で抱きしめる、50リジュほどある巨大なクマのぬいぐるみ。つい『年相応だから仕方がない』とわがままに目をつぶりたくなるほど容姿に恵まれている。
「ひぇ~~! 勘弁してくださいお嬢様ぁ~~」
少年は情けない声を出しながら足を速め、ついに乗船口にたどり着く。

「招待状と乗船券をお見せください」
乗船口で乗務員が笑顔を見せ、乗船資格の提示を求める。この豪華客船はヴェルヌ社が所有するもので、おもにラミリーン湾経由でレミフェリア公国とカルバード共和国の間を行き来する。
現在は共和国の豪商ハルドル・バールンが貸し切っており、今回の乗船にはそのバールン氏が送った招待状と通常の乗船券の両方が必要となる。もっとも、送られた招待状には必ず客室指定の乗船券が付随されており、乗船券のほうはあくまで形式上のものにすぎない。
「グレイ」
少女は少年の名を呼び、暗に招待状と乗船券を出すよう、手で指示する。
「はい、お嬢様。なんでしょうか?」
しかし幼い執事は察しが悪く、その意図を汲み取れていない。
「なーんでお前は、こんなにも愚鈍なの! このクズ! 芋虫!!」
「ひぇ―――!! ごめんなさいごめんなさいごめんなさい……」
思い切り怒りをぶつける少女に、ひたすらに謝る少年。
「はやく招待状と乗船券を出しなさい!」
「は、はいっ!!」
バタバタと荷物を漁る少年執事。しかし慌てていたせいか、せっかく取り出した乗船券が指からすり落ち、宙を舞う。不運なことに、そのときに一陣の風が吹き抜け、乗船券が風にのって遠くへ――
「ああ――――!!」
少年が空中へ手を伸ばし、必死につかもうとするが、それもむなしく、乗船券が港の水面へと落ちた。
しかもその不運はまだ終わってはいない。急にそのあたりに魚影がひらめき、数匹の魚が一気に水面に身を踊りだす。弾けた水しぶきとともに、魚たちは湾にもどり、つられて乗船券も一緒に水底へと沈んでいく。
「あ、ああ、ああああああああああああぁぁぁ―――!!!」
少年の悲痛とも聞こえる叫びが辺りに響きわたる。
ブルブルと身を震わせながら、執事の少年は主のほうへ振り返る。少女はただ、そこに立っていた。何の表情もつくらず、ひと言も発さず、ただ立って、少年を見つめている。あたかも嵐のまえの静けさのように――
「何か、いうことはあるかしら?」
ついに、ひと言。すると少年は壊れたラジオのごとく
「ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい」
と小さな声で繰り返し唱えた。身を縮め、まるで裁きを待つ罪人のように。
「この―――――― 役立たずぅぅ!!!!!」
全身の力を込めた少女の叫びとともに繰り出された鋭い蹴りの一撃。小さな体のどこにそんな力があるのかと思わせるほど、少年の体は大きく宙を舞い、そして“ボシャン――”と、水のなかに落ちた。落水した少年は泳げないらしく、激しく腕をばたつかせ、助けを求める。
「た、助けて…ください…お嬢様……」
バタバタバタ…ブクブク…バタバタバタ…
「今すぐそこから乗船券を探し出しなさい。見つけるまで岸に上がることを許さないわ」
「でも…ボク、泳げ…ません…」
バタバタバタ…ブクブク…バタバタバタ…
「知ってるわ」
「そ、そん…なぁ……」
バタバタ…ブクブク…ブクブクブク……バタつく音が止み、少年は見る見るうちに水の底へ沈んでいく……さすがにまずいと思ったのか、見かねていた乗務員がほかの船員を呼び、少年を引き上げた。しかし少女の怒りはまだ鎮まっていないようで、ふたたび少年を蹴り落そうとする。
「お、お客様、落ち着いてください!」
乗務員が必死に少女をなだめる。
「これが落ち着いていられる!? 私は急用で来れなくなった父様の代わりに来たのよ!」
厳しい視線を少年に向ける。
「船で大事な商談もあるわ、これで乗れなくなったら、どう責任を取ってくれるのかしら!!」
まだせき込んでいる少年はそれを聞いて、すでに青白くなっている顔からさらに血の気が引いていく。それを不憫に思い、乗務員が助け舟を出す。
「とりあえず、招待状のほうを拝見させていただけないでしょうか?」
動こうとする少年を睨んで制し、少女自らやや乱暴な動作で招待状を取り出し、乗務員に渡す。何度もリストと照らし合わせ、乗務員はいう――
「リストにあったクレス・レインハーツ男爵閣下宛ての招待状で間違いありません。男爵閣下の代理として来られたそのご令嬢と使用人でよろしいでしょうか?」
「ええ、私がクレス・レインハーツ男爵の長女、セリア・レインハーツですわ」
乗務員が一礼して、言葉を続ける。
「ではレインハーツ様、乗船券は結構ですので、このままお通りください」
「あら、いいの?」
「はい、どうぞ」
本当は上の判断も仰がずに決めていいものではないが、この場を収めるにはこれが最善の判断だと乗務員は思った。
「命拾いをしたわね、ゴミムシ」

また少年を冷たく一瞥して、少女は船内へ入った。少年は荷物を引き、慌ててあとを続こうとする。すれ違いざまに何度も乗務員に感謝を述べ、相手からは同情と励ましの言葉をかけられた。
船に入った二人はひと言も交わさずに、まるで事前に道を知っていたかのように、足早に自分たちの客室に着いた。部屋のあっちこっちを素早くチェックし、ひととおり終わったところで――
「潜~入~完~了~~」
ひどく緊張感のない、間延びした声が少女から発せられた。
「はぁ~ぅ」
あくびをし、眠たげなその眼からは純真さと可憐さしか窺えず、先ほどまでの高飛車なお嬢様とはまるで別人のようだ。
「なーちゃん、疲れた~。もう寝る」
ぬいぐるみをベッドに放り出し、少女自身も一気にベッドへダイブする。その姿はまさに年相応、いや、それ以上に無邪気なものだった。対して、少年のほうは――
「気を抜くな。任務はここからだ」
まったく感情を感じさせない、氷のように冷たい声。水で濡れた前髪を手で軽く左へどかし、隠していた目があらわになる。それはどこまでも無機質、けれども獲物を睨んでいるような、鋭い目。オロオロするばかりの執事は何処へやら、そこにいる少年は全身から冷酷な気配を発している。少女以上の変わり様といってもいいだろう。しかし――
「さっきのすーちゃんの演技、ヘタだったよ~」
ベッドの上を転がりながら、少女はさりげなく指摘する。心当たりがあるのか、少年は一瞬沈黙し、そしていう。
「任務に支障をきたしていない」

「反応がいちいち大袈裟で、合わせるために、なーちゃんも大変だったよ~、しかも無駄に目立つもん」
言葉からして文句をいっているようだが、無気力な声のせいか、うわごとのように聞こえる。
そう、いまの姿こそこの二人の真実で、先程までの執事とお嬢様はあくまでここへ潜入するための演技に過ぎない。
船の出航前に変な騒ぎを起こせばかえって任務の妨げになる。そのため身分偽装による潜入を選んだ。“組織”の情報網で事前に来られそうにない招待客の情報を掴み、その“娘”を自称する。招待状は、使う紙こそ上質だが、統一された形式で、名前だけ異なって印刷されたもの。そこはまさしく商人らしい合理性を追求した結果だろう。おかげで偽造は簡単だった。
対して乗船券のほうはヴェルヌ社最新の偽造防止技術が詰め込まれており、偽造するにはリスクが大きい。だから乗船口であんな芝居を打ったのだ。
少年が乗船券を落とすのはもちろんわざとで、あのとき風が吹いたのも、魚が暴れたのも、ぬいぐるみの中に隠した戦術オーブメントを使って、少女がひそかに魔法を発動したからだ。結果、目論見どおりに潜入に成功した。
少年の名は《ソードの3》。
少女の名は《ソードの9》。
二人は、殺し屋である。