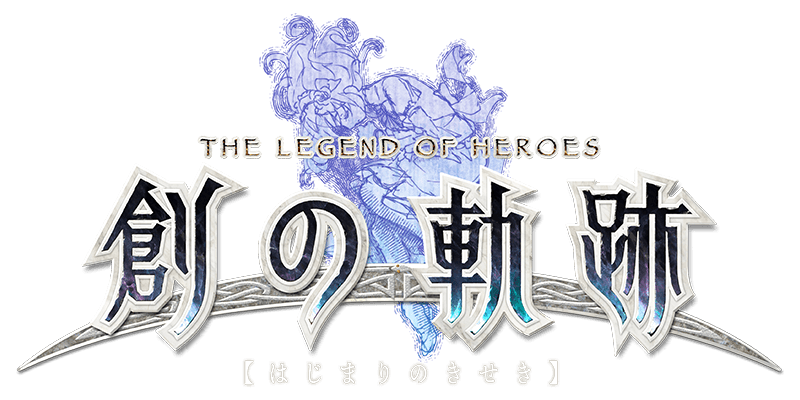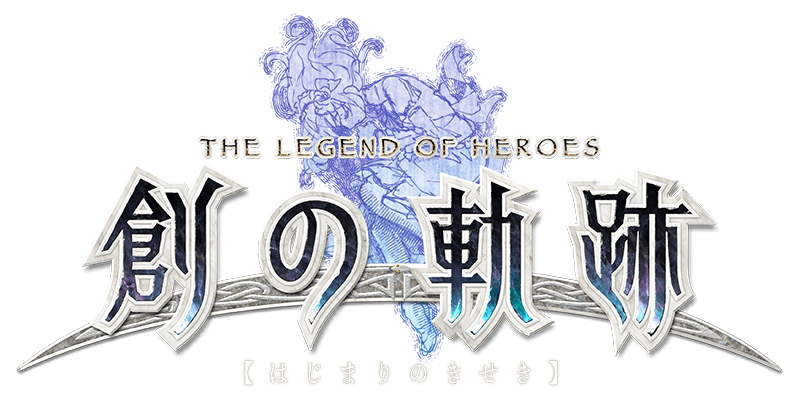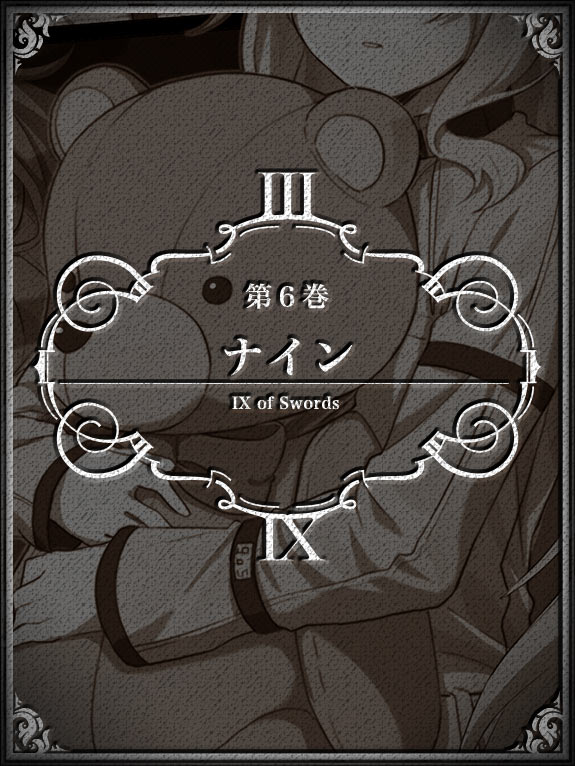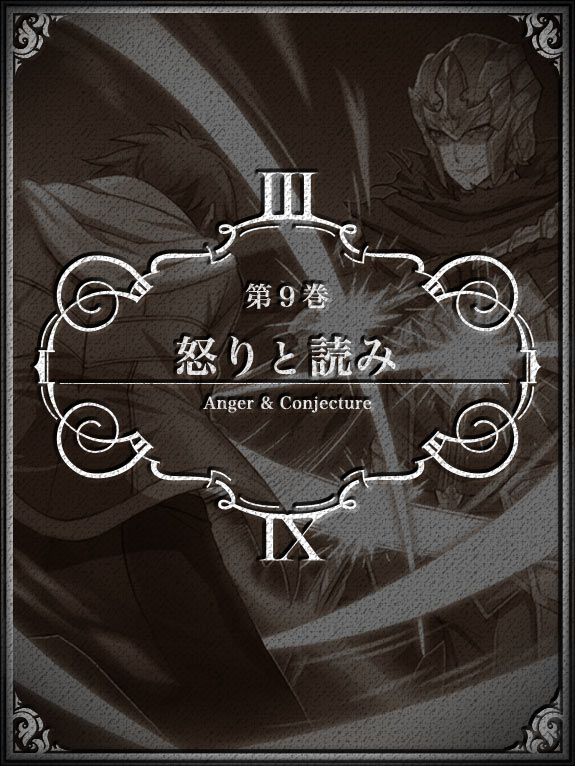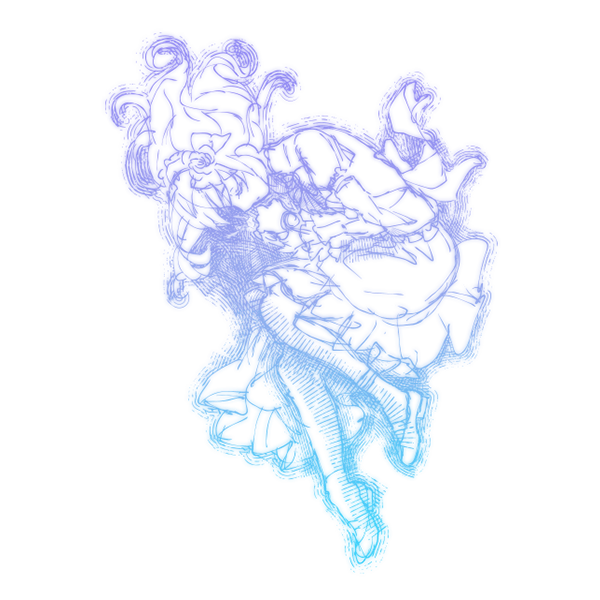貴賓室のなかの貴賓室というべきか、その部屋はだだっ広かった。
ハルドル・バールンはソファーに座り、そっとワイングラスに口をつけてから、不味そうに顔をしかめる。
「無能どもめ。所詮は猟兵崩れ、料金分の仕事すらできんとはな」
彼は正しく現状を理解している。目の前に立っているのは子供二人。
誰も入れるなと命令したし、そもそも外が騒がしくなった時点で察しがついていた。外見からにわかには信じがたいが、この二人が自分の命を狙っている殺し屋で間違いない。理解しているにもかかわらず、ハルドルの顔からは少しも焦りの色がみえない。それはきっと彼の前にある“あれ”が原因だろう。
このだだっ広い部屋でも、“あれ”が存在するだけで狭く感じられる。高さ2アージュを超えるその物体は6本の脚を持ち蜘蛛のように地面を這う。ただし上半身は直立し、そこからさらに4本の腕らしきものが伸びている。全身から金属の光を反射させ、静かな威圧感で場を支配している。
「大きい~」
見上げながら感嘆の声を漏らすナイン。
「人形兵器――!!」
スリーは即座に戦闘態勢を取る。

「フフン、これは俺が闇のオークションから高額で購入したお気に入りだ。どこの組織が流したのかは知らんが、かなりの高性能でね、そのうえでさらにミラを積んで改造したのだ。小隊規模の軍隊相手でも余裕で戦える」
おもちゃを自慢するようにハルドルは上機嫌に笑う。
「猟兵崩れたちはあくまで哨戒程度で、本命の護衛はこっちというわけか」
「そのとおり。こいつが傍にいれば、この船での俺の安全は保障される。そしてこのまま共和国に着けば、あとはどうとでもなる!」
そう言って、さらに声高く笑い出すハルドル。
「愚かな」
「バカなひとね」
べつに自分たちの実力を過信しているわけではない。たとえ自分たちが失敗しても、《黒月》の保護を受けても、“組織”がターゲットとして認識しているなら、彼はきっと逃げられない。
「やれ!! ―――」
ハルドルの命令を受け、人形兵器が動き出す。最初の標的はスリーのようで、一直線で彼に向って突進していく。それを機に、ナインはアーツの駆動にはいる。白兵戦に特化したスリーと違い、彼女は導力魔法の適性も高い。しかし即座に、人形兵器の腕のひとつが銃口に変形し、ナイン目掛けて掃射する。
「!!ッ」
間一髪でそれを回避したが、駆動中のアーツが中断された。スリーは長剣で斬りかかり、人形兵器の注意はスリーにもどる。ナインは素早く移動し、スリーの反対側でふたたびアーツを駆動する。
“ズゥイイン―――”
が、またもや銃口を向けられたナインは、回避のためにアーツの中断を余儀なくされた。どうやらこの人形兵器にはアーツの駆動を探知する高性能のセンサーがついており、反応があれば即座に攻撃するようになっているらしい。2回も行動を邪魔されて、ナインが少し不機嫌そうにいつもよりきつくぬいぐるみを抱きしめる。
「なーちゃん、やめた~、相性悪すぎ~あとはすーちゃんに任せる」
機械相手に毒針を投げつけても意味はない。そのうえアーツの発動までままならないとなると、たしかにナインにはどうすることもできない。それを理解して、スリーは仕方がないと小声でつぶやき、剣を構えなおす。
「じゃあ、戦闘が終わったら起こしてね~なーちゃんもう寝る……」
いつの間にかナインは手頃なソファーを見つけて、ぬいぐるみを枕に寝ようとしている。
「寝るな!!」

思わず大声を上げるスリーだが、ナインは反応しない。人形兵器も脅威ではないと判断したか、スリーにだけ狙いを定めている。
人形兵器の4本の腕はそれぞれ剣、槍、斧、銃に変形し、怒涛の連続攻撃をスリーに仕掛ける。剣で斬り、避けられたら槍で突き、回避方向をつぶして斧で薙ぐ。銃をあまり使ってこないのはハルドルのほうに向けて、彼に敵が近づけないよう警戒しているからだ。
高速での移動と斬撃こそスリーの基本的な戦闘スタイルだが、6本の脚によるバランス性能と瞬発力は金属製の体とは思えないほどの素早さを人形兵器にもたらし、さらに腕が多いぶん、手数はスリーをも上回る。自分の得意領域がまったく発揮できない相手。ナインほどではないが、スリーにとっても決して相性がいいとはいえない。
二本の剣で応戦するスリー。
体格も手数も自分より遥か上の相手に、左手の短剣は防御用と割り切る。降り注ぐ攻撃をいなし、そらし、軌道を変えさせる。そして隙あらばリーチの長い右手の長剣で攻撃する。
激しい攻防がしばらく続く。
何度か隙をついて人形兵器の腕や胴に攻撃を届かせたが、その度に“キンッ――”という音が響き、剣が弾き返される。
「フハハハハハ―― 無駄だ小僧! 装甲も特注品を使っている、貴様らに突破できるはずもない!」
事実、スリーの攻撃は完全に効いていないと言ってもいい。まだほとんど傷を負っていないが、このままではいずれジリ貧になる。そんなとき、寝ているはずのナインが突然声をあげる。
「解析完了」
目を閉じ、ソファーに横たわったまま、ナインは言葉を続ける。声はいつもより平坦に聞こえる。
「腕、第一関節、下5リジュ。脚、第二関節、上3リジュ。腰、回転部中心。左胸、上5分の2、左5分の1」
それを聞いて、最初に反応したのはスリーではなくハルドルだった。彼は焦りの表情を浮かべて叫ぶ。
「貴様! なぜこいつの構造的弱点を知っている!?」
ナインはゆっくりとソファーから身を起こし、目を擦りながら、いつもの調子で答える。
「音で分かるよ~、ちょっと集中する必要があるけど」
「そんなっ、バカな……」
信じ難いといった表情を浮かべるハルドル。対してスリーは冷静だった。当然ナインは解析が目的だということをスリーは最初からわかっている。そして解析が完了するこの時を、彼はずっと待っていた。
「すーちゃん~、やっちゃって~!!」
「ああ、了解だ」
スリーは一瞬身を屈め、鋭く飛び出す。
先ほどよりも高速で長剣を振るい、人形兵器に斬撃を浴びせる。
その一撃一撃がすべてナインの指示した弱点に命中した。すかさず短剣を前に出し、直前と同じ軌道で人形兵器のすべての弱点を、短剣を使ってもう一度斬る――が、結果は前と変わらず、甲高い金属音が何度も響き渡るだけで、相手がダメージを負ったようには見えない。
「クククク……フハハハハハハ―――」
腹を抱えて笑うハルドル。
「弱点を知っても無駄だったようだな、貴様らにはこの装甲を突破することなどできんわ!!」
「いまのは前準備だ」
言って、スリーは左手の短剣を柄のほうから、右手の長剣の鍔に――差し込んだ。
すると、あたかも最初から一体であるかのように、細すぎた刀身も、欠けていた鍔も、これで丁度バランスが取れた、一本の剣となった。ハルドルは呆然とそれを見て、一瞬の沈黙の後、失笑した。
「フ…フフフン、なんだそのおもちゃの剣は? まさかそれで勝てるとでも思ったか?」
ハルドルのいうとおり、二本の剣を合わせて一本にしたところでリーチも切れ味も変わらない。重量が増した分、幾分か破壊力が増すかもしれないが、それでも目の前の敵の装甲を突破できそうにない。これではただのおもちゃだ。
スリーは返答せず、ただ無言で一本となった剣を振る。
斬撃は先ほども斬ろうとした脚の弱点部分に命中した。すると “バンッ――!!” という爆音とともに、人形兵器の狙った脚が爆散した。まるで内側から爆発したようで、火属性のアーツの効果を思わせるが、スリーにもナインにもアーツを駆動した素振りはない。そもそも人形兵器のセンサーも反応しなかった。
「なっ、なにぃぃぃいいいい!!!!!!!??」
ハルドルが驚愕の表情を浮かべる。
もうひと振り、すると―――
“バンッ――!!”
もう1本の脚が弾け飛んだ。
「なんだそれは!!!!!??」
必死の形相を隠せず、彼は叫ぶ。
「この剣は少し特殊なんだ」
スリーはなんの表情も浮かべずに語りはじめる。
「剣と戦術オーブメントが一体となっている。いや、戦術オーブメントより、普通の導力器に近いかもしれない。」
語りながら、その間も手を止めない。
「使えるアーツはひとつだけ、指定位置に爆発を起こすというものだ。ただし発動させるには、分かれた二本の剣でそれぞれ目標の場所を斬る必要がある。相対座標の記録、つまりマーキングだ」
弾かれながらも二本の剣で斬りつけたのは、まさにその“前準備”。
「最後に一本に戻った剣で二重マークしたところに触れ、衝撃を与えれば、爆発する」
位置とタイミングの指定をほかの形で代行し、専用特化型のオーブメントによる自動プロセスと合わせ、アーツ駆動の過程そのものを省略する。手順は面倒だが、うまく使えば無詠唱で高威力のアーツ攻撃を放てる。それがスリーの持つ武器の真価だ。
「そんな……ものが……」
所々火花を散らしている人形兵器はすでにかなりのダメージを受けている。自分の敗北を悟ったハルドルはすぐさま逃げる準備をはじめる。
「戦闘をやめろ! 早く俺を連れてここから離脱しろ!!」
新たな命令を受け取った人形兵器は転向し、ハルドルのところへ向かおうとする。
「させないよ~」
いつの間にか、その蜘蛛のような脚には鋼糸が複雑に絡み合い、がんじがらめになっている。
「終わりだ」
とどめとばかりに、スリーは残りの弱点部位を一気に叩き斬る。爆発が幾重にも重なり、壊れた部品が部屋中に飛び散り、そしてついに、人形兵器は完全に機能を停止し、バラバラに崩れた。ガラクタを踏み越え、スリーは静かにハルドルへ近づいていく。
「ひぃぃ――」
情けない声を発しながら後ずさるハルドル。しかし、彼に逃げ道はないことはもはや明確だ。任務達成の障害になるものはすでにないにもかかわらず、スリーの顔に勝利の喜びはない。
一歩近づく。
手のなかの剣が急に重くなったように感じる。
もう一歩。
足も重くなった。これ以上進みたくない。
さらに一歩。
いつものことだ。あとは“機械”に、“道具”になりきればいい。問題ない。
最後の、一歩。
「本当はアンタにあんな解説をしても意味はないけど、せめてどんな相手に殺されるかくらい、知る権利はあるだろう」
煉獄で呪う相手のことくらい――
「オレの名はソードの3」
心臓へひと突き。
「“組織”の、殺し屋だ」
…………2階ホールの混乱を収め、船の警備員たちは3階へ乗り込もうとする。その気配を感じ、目的を達成したスリーとナインは窓を割り、海に飛び込んだ。
「飛行船じゃなくてよかったね~ もし空中だったら、こんな脱出は出来なかったよ」
「そうだな」
それこそ高性能な専用飛行艇を持っていて、そこに飛び移らない限りは。この世界のどこかに、そんな風に単独任務を行うヤツはいるのだろうか。
「すーちゃん」
そっとスリーに呼びかけるナイン。
「あのひとは悪人だよ~、悪徳商人」
船のほうを見る。誰のことを指しているかはいうまでもない。
「ああ、分かっている」
任務前の資料でよく知っている。ミラのために悪事の限りを尽くした、死んだほうが世のためになるような人種だ。だが――
「だが、関係ない」
そんなことは言い訳にならない。悪人だろうと善人だろうと、“組織”からの命令なら殺した。今までそうしてきたように。
「そう」
ナインはそれ以上何も言わなかった。彼女はぬいぐるみから何かを取り出し、それに息を吹き入れる。しばらくすると、その“何か”が一人用サイズのゴムボートということが分かった。今度はぬいぐるみを抱き枕にして、ナインはゴムボートに寝そべる。
「じゃあ、なーちゃんは寝る。あとはお願いね~」
それは暗に、スリーに「岸まで押していって」という意味を持つ。
「自分で泳げよ」
文句を言いながら、そんな彼女の姿を見て、スリーは少しだけ心が軽くなった感じがした。スリーとナインは1年以上行動をともにしている。スリーのほうが少しだけ年上で、少々天然なところがあるナインのことを時々妹のように感じる。任務のときは頼りになるパートナーだ。
だがスリーは分かっている。
妹のようであり、パートナーでもある彼女は
――― 決して信用してはいけない。