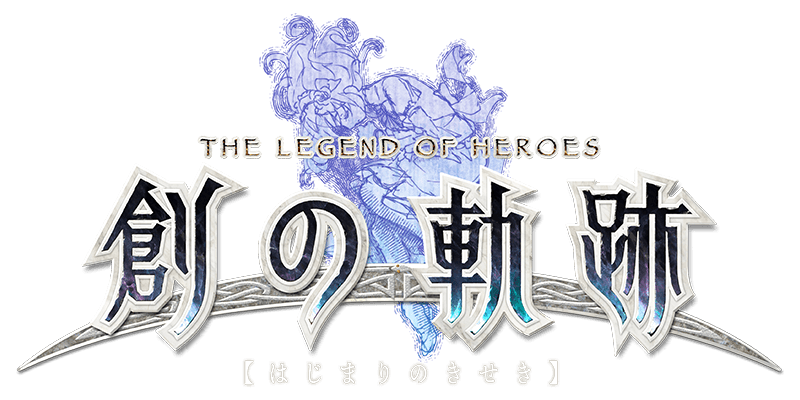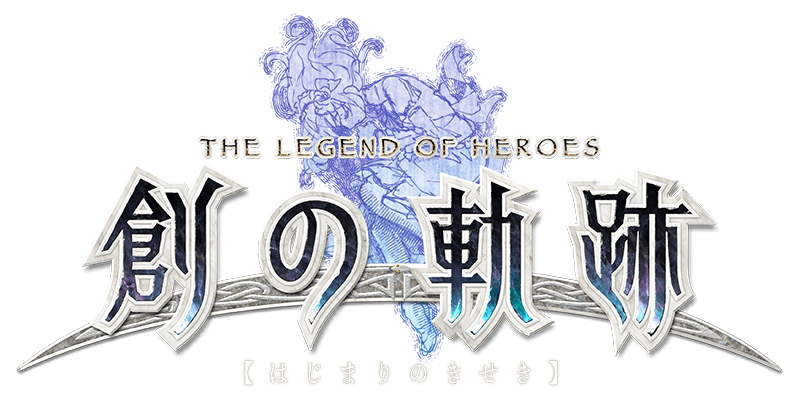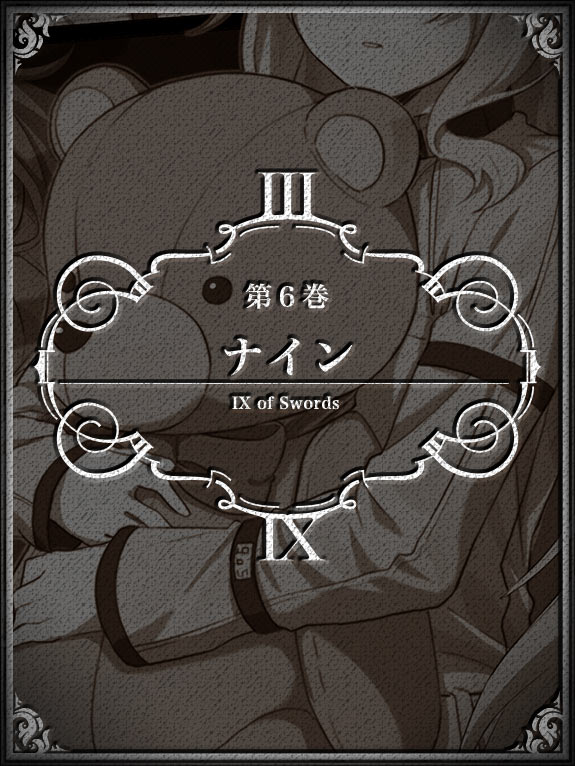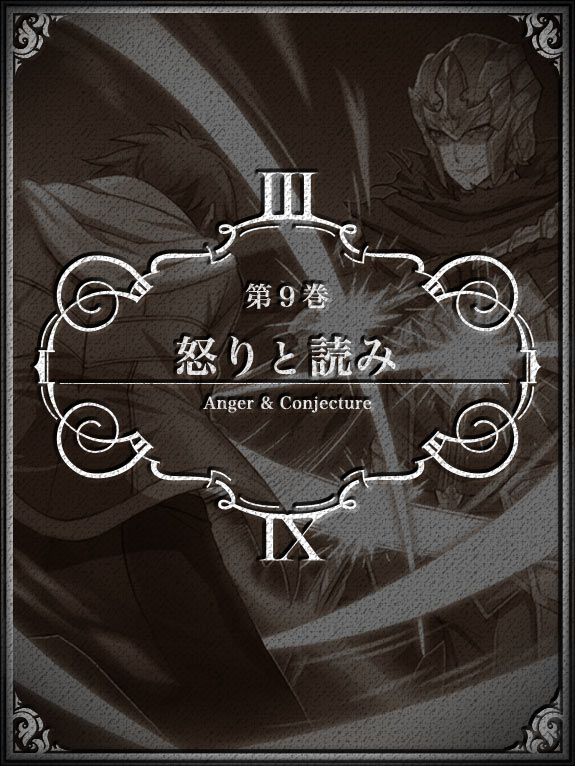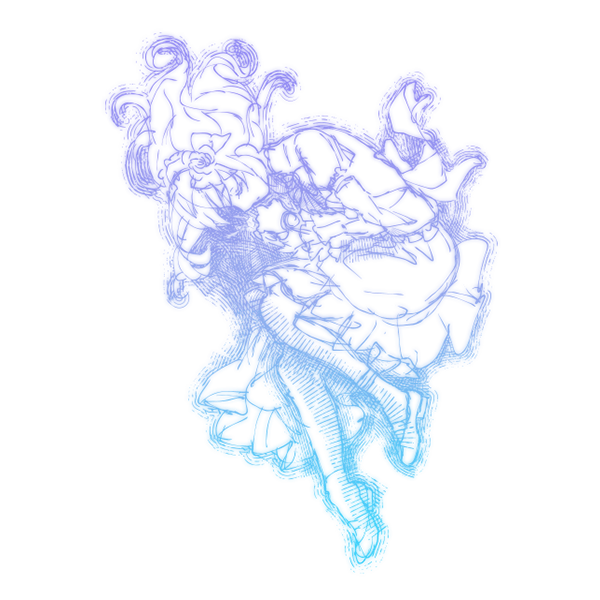“ヤツら”がオレを追いかけてくる。
今までオレが殺した人たちだ。
頭を切られ、心臓をえぐられ、胴体を両断され、それでもオレを追いかけてくる、無数の死体たち。
どこかの政治家も、どこかも貴族も、どこかの商人も、どこかの金持ちも。
来るな来るな来るな来るなぁ!!!!!―――
必死に剣を振る。
斬って斬って両断して爆ぜて――
それでも、“ヤツら”は止まらない。
肉片になっても、骨になっても、胃も肺も腸も脳みそも、全部蠢いてオレに向かってくる。
波になってオレを呑み込もうとする。
走って逃げて逃げて逃げて逃げて――
そして前方に“アイツ”がいた。オレが殺した、“アイツ”が。

『よくも俺たちを殺したなぁ!!!』
オレを突き飛ばし、オレの首を絞める。
放せ放せ、オレを放せ!!
必死にもがくが、解けない。
腐った体液がオレの体に滴り、皮膚を溶かす。
そして、“波”に呑まれる……
オレはただ、“人間”になりたいだけなんだ――
悪夢から目覚める。
荒く息をし、全身から嫌な汗が噴き出て、込み上げる嘔吐感を無理矢理おさえ込む。
任務が終わった夜はいつもそうだ。何回やっても薄れない、殺人への嫌悪。
いつまで経っても拭えない、手のひらの感触。だけどやらなければならない。
オレたちは道具だ。意思は求められていない。
求められるのは人を殺す力と命令への服従。
ただ“組織”が命じるままに、人を殺す。その一点にのみ、存在意義が与えられている。命令への拒否も、“組織”からの逃走も、“死”を意味する。
―――“組織”。
その本当の名を口にすることすら憚られる、「裏世界」の殺し屋集団。
おもな業務が暗殺だからそういう認識になっているが、本当の目的は別にあるかもしれない。ただしそれが何なのか、下位構成員――道具であるオレには知る由もない。
構成員のほとんどは子供のころから“組織”に隷属している。ワケありの子供を“かき集め”、“養成所”というところで戦闘訓練を受けさせる。そのなかの多くは過酷な訓練に耐えきれず途中で“脱落”するが、運よく生き残れたら、“名前”を与えられ、正式に下位の構成員として認められる。
オレもそうだ。7歳で無理矢理“組織”に入れられ、10歳で“養成所”を出た。
元々の名前は“養成所”に入ってすぐに捨てさせられた。名乗るのはもとより、口にするだけで厳罰の対象となる。“自分”というものがない、単に“大勢いる道具候補のなかのひとつ”でしかない日々だった。
構成員になって、やっと名前が与えられる。しかし、それも“道具”であることの証明でしかない。「タロットカード」の「小アルカナ」、その56枚の中の1枚が、下位構成員に与えられる名前だ。
オレの場合はソードの3。少しも人間味のない名前だけど、ないよりは、マシだ。
ちなみに幹部とごく一部の特殊な力を持つ者には「大アルカナ」の名前が与えられる。その戦闘力はオレたち下位構成員をはるかに凌駕し、高位遊撃士以上の実力を持つと噂されている。
宿の部屋を出て、オレは隣の部屋の気配を窺う。ナインはまだ寝ているようだ。ちょうど報告の時間だったので、そのままひとりで宿を出る。
“組織”の下位構成員は基本的に二人一組で行動する。オレのパートナーはソードの9、ひとつ年下の少女だ。通常3年から5年、もしくは途中で“脱落”する“養成所”を1年で卒業した“天才”。情報収集、戦況分析、演技、潜入……あらゆる面で優れた才能を持ち、針と糸を武器とするその戦闘スタイルは対人戦で優位に立ち回れる。こと暗殺に関しては、その適性はオレの比ではない。オレと組んだ、最初の頃はぎこちなかったが、いまでは任務中で最も頼りにしているパートナーである。
――同時に、オレが最も警戒すべき対象でもある。
二人一組という制度は任務の成功率を上げるためのものだが、それ以上に、互いを“監視”させることを目的としている。
裏切りが“死”を意味する“組織”。
自由はなく、あるのは“道具”としての一生のみ。しかし、“組織”のなかにはある特殊なルールが存在する。
一、パートナーによる組織の裏切りを察知できた場合、上に報告し証拠を提示する。
二、その当人を殺す。
このふたつを達成できた場合に限り、特例として“組織”から自由になれる権利が与えられる。
下手に逃走してもいつ“組織”の追手に殺されるかわからない。確実に自由になりたいなら、逃走よりも、常にパートナーの行動に目を光らせたほうがいい。最悪パートナーに“組織”を裏切る気がなくても、バレないように証拠をでっちあげられれば、自由を手にすることができる。
最も警戒すべきは敵ではなく、隣にいるパートナー。
“組織”を裏切ろうとせず、パートナーの裏切りを常に警戒する。それが生き残るための絶対条件だ。
オレはそのことを、身をもって知っている……3年前、オレは一度“組織”からの逃亡を試みた。
……いや、正確にいうと「オレたち」だった。
オレと、あの時のオレのパートナーである少年《ソードの1》。
エースはオレのひとつ年上の気さくなヤツだ。人当たりがよく、オレとはとくに気が合っていたし、パートナーになってからは、オレにとっては兄貴分のような存在だった。身の丈ほどもある巨大な剣を軽々と振り回し、時には敵を屠り、時にはその剣身を盾にして敵の攻撃からオレを守ってくれた。「エース」の名に相応しい実力者だった。
エースはオレと同じく、殺人を嫌悪していた。そんなオレたちが、“組織”からの逃亡を決め込んだのも自然の流れだった。

パートナーに売られるから“組織”を裏切れない。
だったらパートナーと一緒に“組織”を裏切ればいい。
そうすれば二人とも助かる。
そう結論付けて、二人で逃亡を計画した。
他のペアの目が届かないある遠出の任務で、それを決行することにした。
最初はうまくいったつもりだった。普段の活動地域から離れたエレボニア帝国に入ったことで、安全だと思い込んだ。しかし、そこにも“組織”の“目”があるのは誤算だった。すぐに他のペアが追手としてあらわれ、戦闘となった。それでもエースとうまく連携し、2回も追手を撃退した。
でも、3回目に現れた追手はオレたちのような下位の戦闘員ではなく、“管理人”だった。圧倒的な力の前で、オレとエースはなす術もなかった。重傷を負い、命からがらの状態でその場から逃げ出した。もう先はない。次に敵と遭遇したら、終わりだ。洞窟で身を寄せ合うオレとエースは言葉を交わさずとも、互いにそのことをよく理解していた。
「なあ、エース」
「なんだ、相棒」
最後の会話になるかもしれないと思って、オレは言葉を紡ぐ。
「オレは、これで悪くないと思う」
「なにそれ」
「未練も悔いもたくさんあるけど、それでもさ」
エースは静かにオレの言葉を待つ。
「それでもオレは、お前と最後まで一緒に戦って死ねるなら、悪い気はしない。“道具”として人を殺し続けるよりは、何万倍もマシだ」
篝火が揺らめく。しばらくの沈黙の後、エースはつぶやく。
「そうか……いままでありがとうな、相棒」
「オレのほうこそ、いままでありがとう」
これで話すべきことは話した。もういつ敵が来ても、オレは最後まで戦える。そして――
「それならさ」
突然空気が変わったような錯覚に襲われ、エースの冷たい声が聞こえる。
「俺のために死んでくれ――」
一瞬、言葉の意味が分からなかった。すぐにそれが「一緒に戦って死のう」という意味だとオレは勝手に解釈し、確認のためにエースのほうへ振り返る。その視界に映ったのは―――

―――振り下ろされようとしている巨剣だった。
とっさにそれを回避し、一瞬前にオレがいた地面が砕かれる。
「どうして!? エース!!」
「どうしてだと? “組織”のルール。パートナーに関しての最後の項目、忘れたか?」
最後の項目。
自分には無縁なものだと思い、ずっと意識していなかったその内容を思い出す。
――パートナー二人がともに“組織”を裏切ったとき、片方が自らパートナーを殺し、その死体を献上した場合に限り、“組織”に許される。つまり、裏切り者二人が逃亡に失敗したとしても、互いに殺し合えば、ひとりだけ生き残ることができる。そしてそれを、まさに今エースが行おうとしている。
そこまで理解して、それでもオレは、同じ言葉しか発することができなかった。
「どうして……エース――!」
「相棒、お前とパートナーを組めたことは、煉獄の底で生きるような日々のなかで、唯一の幸運だった。お前と一緒に人間になりたかった、自由になりたかった」
「それなら――」
「それでも俺は、死んではいけないんだ!生きていかなきゃいけないんだよぉ!!!」
そう叫びながら、エースは巨剣を振るいオレに斬りかかる。幾度もオレを死地から守ってきたその剣は、今度はオレの命を
「死ね! スリー――!!!!」
「あぁぁああああああああ!!!!!!」
オレも剣を振るう。
悲しみと絶望に呑まれ、ただ本能に従い、目の前の“敵”に応戦する………
………
……
それからどんな風に戦っていたのか、憶えていない。
怒りと悲しみに身を任せ、必死に、無様に、獣のように斬って叫んで引きちぎっていた。
そして気が付いたときには、そこにはエースの死体が転がっていた……
こうしてオレは再び“組織”の“道具”になり、今日まで生き永らえた。
“人間”になる願いを諦められず、同時に人間が信じられなくなった、出来損ないとして。