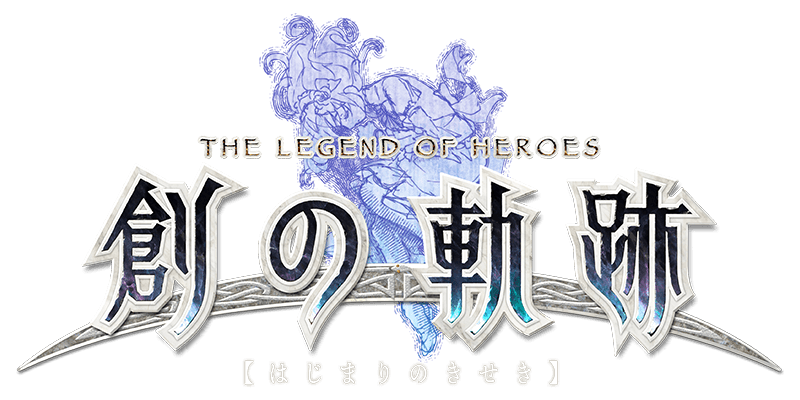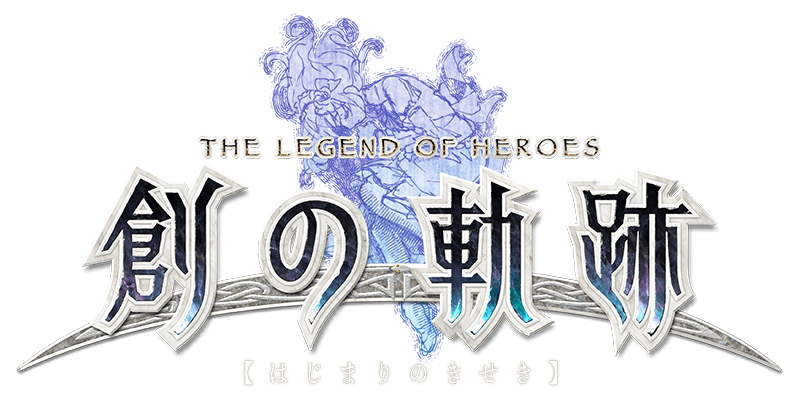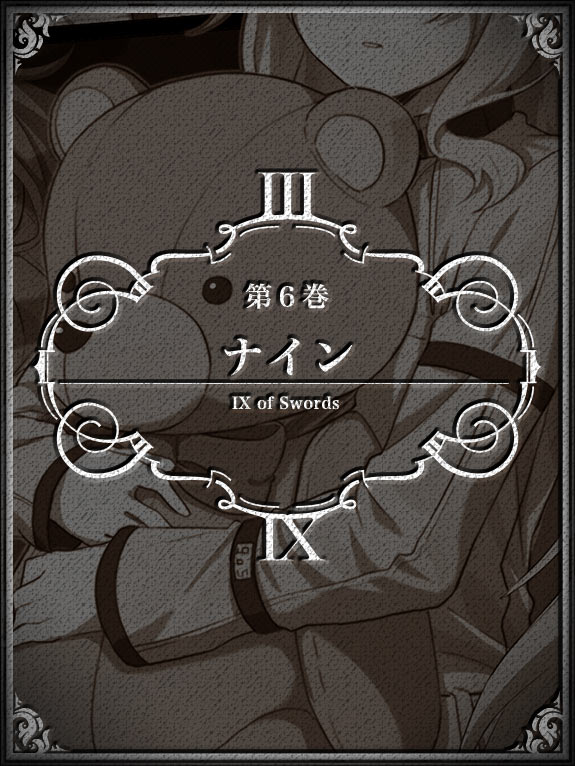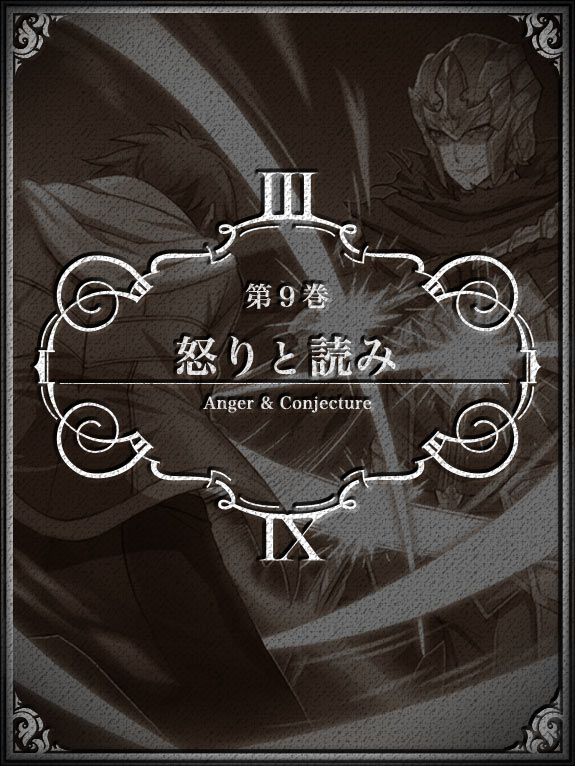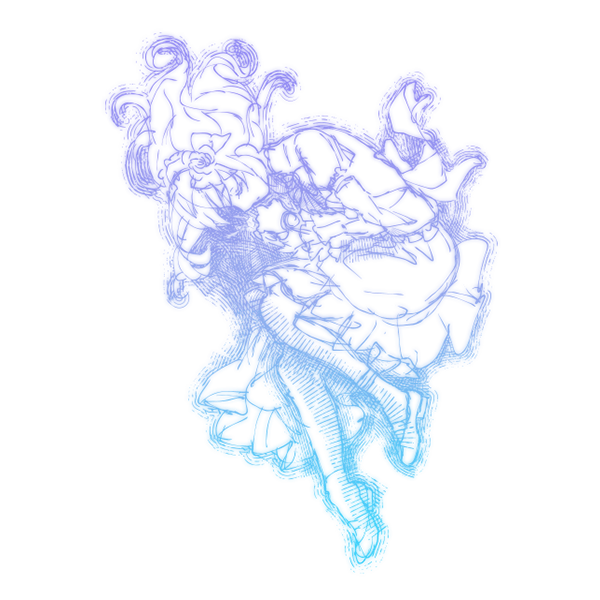まだ未明の空、町中を歩くひとはほとんどいない。
宿から出たスリーは冷たい空気を肺に吸い込み、淀んだ気持ちを何とか洗い流そうとする。
ここはレミフェリア公国の国境にある町ルーゼント。
公国と共和国で活動するスリーとナインにとってはなかば拠点のような場所である。
東に進めば共和国との国境門があり、西に進めばごく一部の人間しか知らない危険な山道があるが、門を通らずに共和国にはいる道もある。
報告のため、スリーはひとりで指定された場所へ向かう。
そこは風化した岩が並ぶ小さな丘だった。山奥にあるため、ひと気がまったくない。
そこで待っていたのはひとつの黒い影、いや、黒い装束の男だった。
全身を古びたローブで覆い隠しているため、顔どころか体つきさえ確認できない。異様としかいえない装いだが、それだけでは到底説明不可能な威圧感を周囲の空間に与えている。
「報告に参りました、“管理人”」
「聞こうか」

“管理人”と呼ばれているこの男は、スリーたちを管轄する“組織”の幹部のひとり。
大アルカナ《皇帝》の名を持っているが、“組織”の中ではむしろ“管理人”と呼ばれることが多い。
“管理人”の呼称のとおりに、彼はスリーたち下位戦闘員を管理している。任務を与え、報告を受け、“道具”を直接運用している存在である。
スリーは先日の客船での任務の詳細を“管理人”に報告する。
それが終わったあと──
「次は」
「はい、ソードの9の行動に関して」
パートナーの行動報告にはいる。
これも定期報告の一環で、パートナーを監視させ、そのあと別々に報告させる。自分の行動報告とパートナーによる監視報告に少しでも食い違いがあれば“組織”に疑われる。
こうして別々に報告させることで、知らないうちに自分の裏切り行為が“組織”に筒抜けになってしまうという恐怖を与えることも、その目的のひとつである。
「以上です」
「うむ、いいだろう。次の任務は追って指示する」
「はい、それでは」
スリーがその場から離れようとしたとき、突然背後からの低い声で呼び止められる。
「スリー」
振り返るが、相変わらず“管理人”の顔が窺えない。
「あれから3年、また同じことを考えていないだろうな」
瞬時、背筋に冷たいものが走る。窒息するほど濃密な殺気がスリーを襲う。
“あれ”が指すのはいうまでもなく、3年前スリーが行った逃亡未遂のことだ。
“管理人”エンペラーはよく自ら“粛清”を行う。その圧倒的な力の前に、裏切り者はただ無残に殺されることしかできない。そのため、彼は“組織”のなかでも恐怖の対象と見なされている。
3年前にスリーとエースを追い詰めたのもまさに彼だった。
その人物があのときと同じ殺気を放ち、スリーを問い詰めている。まさか自分の企みに気づいたのか?
いや、慎重にやってきたのだ。もし何か証拠を掴んでいたら、とうに自分は殺されている。
これは……試されているのだ。少しでも動揺すれば、そこで終わる!
「ご冗談を……あのような愚かな行為は二度とあり得ません。所詮自分はひとを殺すことしか能がない、ただの“凶器”ですから」
自然な呼吸で、息を乱さず、計算し何度も訓練した口元の形や視線の角度……すべてを完璧に演じる。
しばしの沈黙のあと――“管理人”が口を開いた。
「ならばいい」
すると重苦しかった殺気が嘘のように霧散し、全身にのしかかった重圧も消えた。
「君には期待している」
「はい、ご期待にお応えできるよう精進します」
そして今度こそ、スリーはその場を離れた。
「何とか、なったか……はぁ…」
宿に戻ったスリーは息を吐き、ベッドに倒れ込む。
とくに何かしたわけではないが、極度の疲労を感じる。それほど“管理人”とのやり取りで精神を消耗したのだろう。
それもそのはず。なぜなら彼は自分の真意を隠しているからだ。
そう、スリーは再び逃走を計画している。
3年の歳月は彼から自由の意思を奪うことは出来なかった。むしろ日に日に増して、“人間”への憧れが膨らむ一方だった。血に濡れた両手はどんどん重く、醜くなっていく。自分は人間の形をした“道具”。しかしこのままでは、その形すら保てなくなり、ただひとを殺すための“装置”となり、“怪物”になるのだとスリーは思った。それはあまりにも恐ろしい未来だ。
――今度こそ逃げ切ってみせる!
そのための絶対条件は“管理人”との正面衝突を避けることとパートナーのナインに逃走の計画を隠し通すこと。
もちろんそれはナインをひとりにして、置いていくことを意味する。
何度も生死を共にしたパートナー。
自分よりも幼く、才能に溢れていながらもどこか抜けているような女の子。
不思議と放っておけないような感情がスリーのなかに渦巻く。
何回かナインに打ち明けようとしたが、その度に巨剣を掲げ自分へ振り下ろそうとするエースの姿が脳裏を過ぎる。あんな思いは、もう二度とごめんだ!!
だから―――これでいい。
雑念を振り払い、スリーは逃走の準備に戻る。
「信じられるのは、自分だけだ」
………………夕方になり、陽がだいぶ傾いてきた頃。前々から準備していたおかげで、スリーの最後の支度はすんなりと終わった。
決行は今夜。
ナインが寝入ってから町を出て、山道のほうから国境を超える。
共和国にはいってからは導力車での移動になるが、事前に用意したレンタル車を使って北部の大都市に行く。そこから国際定期飛行船でリベールへ向かう。その後のことはまだ決めていない。しばらくリベールに留まるか、それともレマンあたりに向かうか、とにかく今いる場所から遠く離れたほうがいい。下っ端の自分では“組織”の全貌なんて分からない、それでも必ず逃げ切って見せる!
カァ――、カァ――
そうスリーが勢い込んでいたところで、1匹のカラスが窓から侵入し、部屋のなかを旋回し始めた。
「これは……」
その脚にさげている独特な装飾を見て、スリーは顔をしかめる。
それが意味するところは――“管理人”からの召集。
「こんな時間に?」
まだ報告を終えて数時間しか経っていない。
「新しい任務の指示か?」
うまく言い表せない不安に駆られるスリー。しかし無視するわけにもいかない。
計画通りなら、追手が動き出すまでにかなりの距離を稼ぐことができる。だがいますぐ逃げても、召集を拒否した時点で叛意ありと判断され、すぐに追手が来て、呆気なく一巻の終わりとなってしまう。
意を決し、スリーは指定された場所へ向かう。
その場所は朝方と同じ、山奥の小丘。
朝の静寂な不気味さと打って変わって、夕陽に照らされた岩は遠くからだとまるで燃えているように見える。
そこではふたつの人影がスリーを待っていた。
ひとりは“管理人”。
前と同じく古びたローブを身に纏うその姿は《皇帝》よりむしろ《隠者》と言ったほうが適切に思える。
もうひとりは、大きなぬいぐるみを抱えた幼い少女――ナインだ。
着ている服は先日のドレスと似たような意匠を感じられるが、装飾が少なめで、幾分か動きやすそうに見える。
新たに任務を指示するなら、ナインがここにいても不自然ではない。
ただ、わずかに普段と違うその雰囲気が、スリーの不安をさらに加速させた。
「──来たか」
「はい、ご用件は何でしょうか?」
いつもと同じやり取り。しかし、それがすぐに違うものになる。
「弁明を、聞こうか」
「べん…めい?」
「君の裏切りはすでに告発された。そこのソードの9によってな」
「なっ!?」
言葉を失う。
予想しうるすべての事態のなかでも最悪な展開が、目の前で形となってしまった。
絶望が波のようにスリーに襲ってくる。またか、またあの時と同じか?
またオレは裏切られ……いや違う。ナインとは別に何の約束も交わしていない。
これが彼女の仕事で、オレもそれを承知したうえで彼女を信用しなかった。
パートナーとはそういうものだ。
ただそれだけの話さ。それだけの、話なんだ。
「これはきっと、何かの勘違いです!」
無駄だと知りながらも、スリーは何とか弁解しようとする。
「言い逃れは出来ないよ、すーちゃん。いいえ、スリー」
言葉を発するナイン。いつもの眠たげなテンションとは真逆の、冷徹な声をスリーに向ける。
ナインはぬいぐるみから1枚の紙きれを取り出し、スリーのほうへ掲げる。
「これは、あなたが予約したリベール王国行き、明日正午発の国際定期飛行船のチケットよ」
「!!?ッ」
衝撃とともに「チケットはオレが持っている!」と叫びたくなったが、当然そんなことをすれば自爆にしかならない。
スリーの疑問に答えるようにナインは言葉を続ける。
「あなたのところにあるチケットは偽造した贋物。私がすり替えたの」
先日の任務で使った手口を、まさか自分がやられるとは。
「ちなみにそのチケットを取るために使った名義は、1年前の任務で偽造に利用したジェニス王立学園の生徒、ラインズ・フォーゲルトだよね? そのときの書類をまだ持っているということは、かなり前から逃走計画を企てていたのかな?」
やはりナインは天才だ、と場違いな感想がスリーの脳裏に浮かぶ。
ここまで見破られていては、もはやどんな弁解をしたところで意味はないだろう。
それでも、スリーにはまだひとつだけ納得し難いところがある。
いくらこれが仕事でも、いくらナインが天才でも、自分もかなり慎重に行動してきたはずだ。
にもかかわらず、こうも簡単に見破られてしまった。何故だ?
「どうしてバレたんだろう、といった顔ね?」
小さく笑うナイン。その言葉のなかに嘲りが含まれているのをスリーは感じた。
「ずっと、あなたのことを見ていたからよ? あなただけを、ずっと見つめていた」
もちろんそれは甘い言葉などではなく。
「見て、見つめて、観察して、監視して……あなたが馬脚を露すときを、今か今かと待っていたわ。それこそ、あなたとパートナーになったその瞬間から、ずっとね」
ナインが何を言おうとしているのか、スリーには分からなくなってきた。
「そして、あなたはこうして実際に“組織”を裏切ったのだけど、もし本当にその気がなくても、そのうち私がでっち上げていたでしょうね」
“管理人”がこの場にいることも構わず、ナインはそう言い放った。
スリーはますます混乱する。仕事として自分を監視していたのならまだ理解できる。だが、これではまるで最初から自分に悪意を持っていたような……そこで、しばらく沈黙していた“管理人”が低く笑いだした。
「そうか、君はまだ知らないのだな、彼女のことを」
“彼女”がナインのことを指しているのは分かる。しかし“知らない”とは、何のことだ?
ナインのほうを見る。するとスリーはいままで一度も彼女から感じたことのない、憎しみをこもった視線に思わず戦慄する。
「あなたが殺した元パートナー、ソードの1は、私の、実の兄よ」

一瞬、深い海の底に沈んだような錯覚に、スリーは捕らわれた。
朦朧とした意識は正常な思考を許さず、潰されそうな重圧のなかで息もできない。
「これでようやく、お兄ちゃんの復讐が叶う」
ナインが、エースの妹?
彼女は最初から3年前のことを知っていて、オレに目を光らせ、オレのそばで機を伺っていた。
オレに――復讐するために。
まるで口が言葉を発する機能を持っていることを忘れたかのように、スリーはただ茫然としている。
「もう答え合わせは十分だろう。次は粛清の時間だ。さあ、ナイン。ルールに従い、パートナーであり告発者である君が殺すのだ」
“管理人”の言葉を聞き、ナインは一歩前に出る。
「我が手を貸してもいい、褒美もそのままだ。ただ、トドメだけは自分で刺せ。そうすれば、晴れて君は自由の身となる。手放すには実に惜しい才能だがな」
“褒美”。
それは、裏切り者のパートナーを告発し殺すことで与えられる“自由”という名の権利。
今のナインはまさにスリーが欲してやまないその“自由”に、手が届こうとしている。
「いいえ、私ひとりにやらせてください。兄の仇は、この手で討ちます」
「いいだろう」
また一歩、ナインは前に出る。
クマのぬいぐるみから毒針を取り出し、素早くスリーへ投擲する。
腰から剣を抜き、毒針を振り払うスリー。そこで一気に距離を詰めるべきだったが、彼は一歩も動かなかった。
そもそも防御したのも、体に染み込んだ戦いの勘がもたらした反射的な動作で、彼自身は意識していなかった。
戦う意思はない。それは相手がナインだからかもしれないが、それ以上に、戦っても意味がないからだ。
たとえナインを倒しても、その後ろにいる“管理人”――《皇帝》には決して勝てない。
自分がここで死ぬ運命はもはや覆らない……ナインは再び毒針を取り出し、先ほどの倍の数をスリーに向けて投擲する。
スリーは2本目の剣も取り出し、そのすべてをさばく。
――そうか、なるほどそうか、これが因果応報ってヤツか。
するとナインのほうがスリーに接近し、さらに攻撃を仕掛ける。
――経緯はどうあれ友を殺して生き延びたオレに、“自由”になる資格が、“人間”になる資格が、あるわけもないか。
針と糸を併用したナインの攻撃。
普段ならスリーが接近戦でナインに後れを取ることはないが、ほぼ無意識で応戦しているだけの状態であれば話が違う。
いつの間にかスリーの首に、鋼糸の輪が掛かっていた。
――だったら仇としてオレが殺されるのも、当たり前か。ナインの指が動き、輪が収束する。

「これで、終わりよ」
もはやここまでだと理解し、スリーはただ、静かに死の瞬間を待つ――
しかし、そのときが訪れることはなかった。