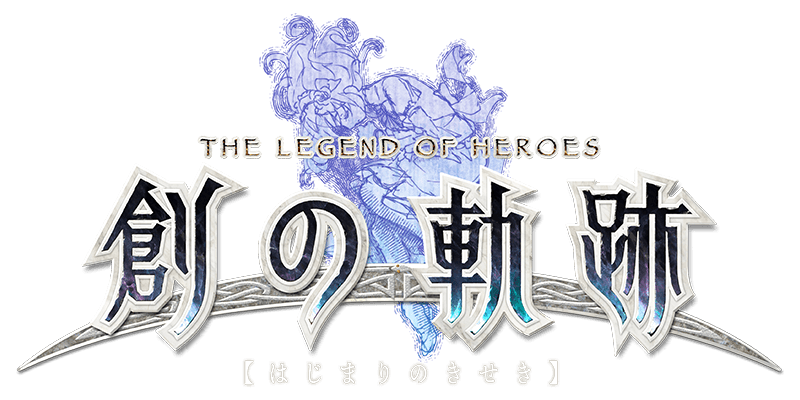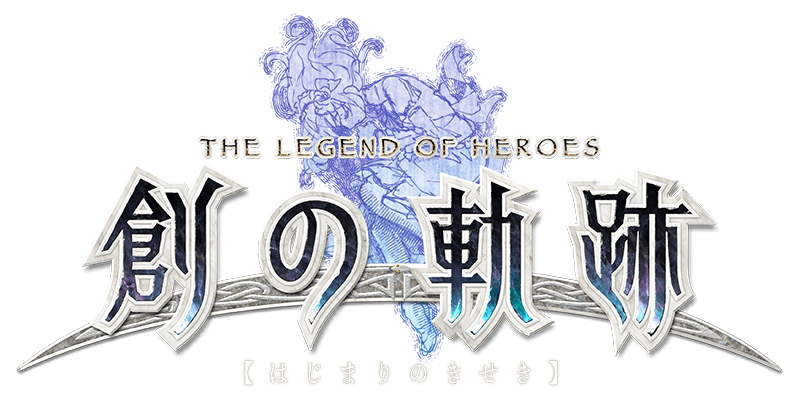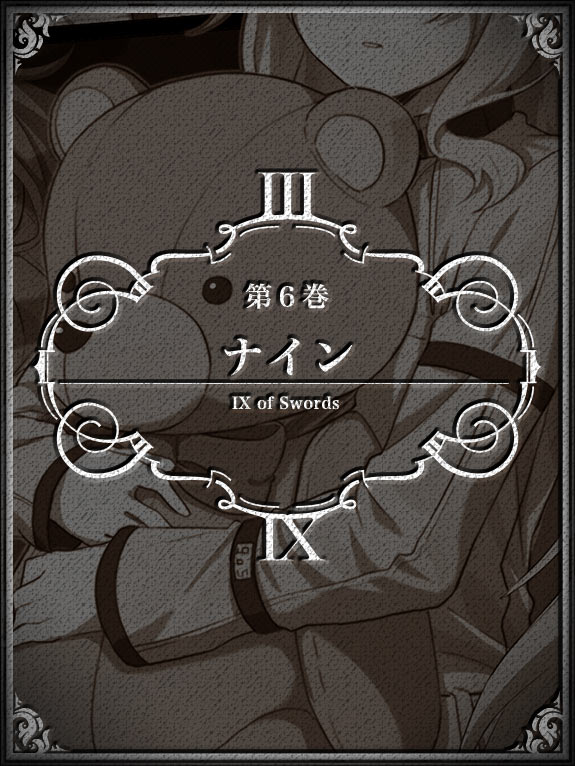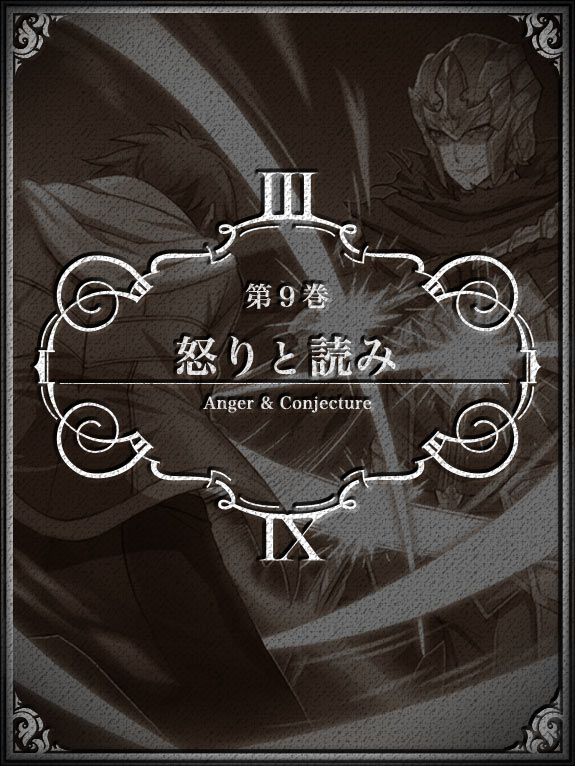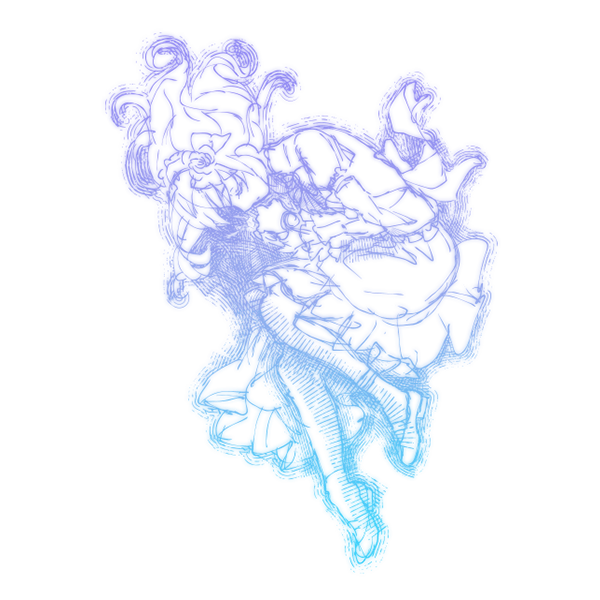私が生まれたすぐあとに、母が死んだ。
父と兄の3人で暮らしていた。
物心がついた頃から父はひどいやつだった。
母が遺したミラを浪費して、ろくに働きもせず、酒に溺れる毎日だった。
機嫌が悪いときは、よく家のなかで暴力を振るった。
私の世話は全部お兄ちゃんがしてくれた。
家のなかでも外でも、お兄ちゃんがいつも私を守ってくれた。
こんな家でも、お兄ちゃんと一緒ならやっていけると、幼い私は思った。
だけど、そんな生活はいつまでも続くことはなかった。
ミラが底をつくと、父はお兄ちゃんと私を働かせようとした。しかし年端もいかない子どもが稼げる額なんてたかが知れている。
そこで父は、あろうことかお兄ちゃんを“手放した”。そのときから、私は父のことを家族だと思わなくなった。
しかし、ほかに頼りもなく、お兄ちゃんがいつか帰ってくるかもしれないという淡い期待を抱いて、私はあの家に残るしかなかった。
それから3年くらい過ぎた頃だろうか。ある日、お兄ちゃんからの手紙が届いた。
とても厳しい環境だけど何とか生きていると、そんなことが書かれていた。
そこに書いてある通りの方法で、私もお兄ちゃんに手紙を送れるようになった。ようやくお兄ちゃんとの繋がりを取り戻すことができて、すごく嬉しかった。
お兄ちゃんが“組織”と呼ばれているものの管理下で、無理やり人殺しの仕事をしていることを知った。文字を通して、その苦しみが痛いほど私に伝わった。
“組織”の管理が厳しくて、こうやって手紙が交わせたのも、お兄ちゃんのパートナーのひとが協力してくれたおかげだそうだ。
その“パートナー”のことを、お兄ちゃんはよく手紙に書いていた。
相棒で、親友で、歳が近い弟のようなものだとか。そのひとの話のときだけ、お兄ちゃんの文章が少し暖かく感じた。
いつの間にか、私もそのひとに会ってみたいと思うようになった。
だけどお兄ちゃんとすら会えないこの状況で、それは無理なことだと分かっていた。
そんな手紙をやり取りする日々がしばらく続いた。
しかし、それも長くはなかった。
家のミラがまた尽きたのだ。今度は私の番だな、となんとなく思った。
そのことをお兄ちゃんに伝えると、それで決心がついたようで、お兄ちゃんはパートナーのひとと一緒に“組織”から逃亡することを決めた。
「必ず戻る」とか、私を「この家から助け出す」とか、そんなことばかりが綴られた手紙の最後には、2行だけ不吉な言葉が並んでいた。
「たとえ逃亡が失敗しても、必ず相棒だけでも生かしてみせる。何かあったら、あいつを頼れ。」
それがお兄ちゃんからもらった、最後の手紙だった。
結局お兄ちゃんは戻らず、思ったとおり、私も父に“手放された”。
父は何か危険なクスリに手を出していたらしい。
恐らくそのうちにまたミラが尽き、そのときこそ、彼は身の破滅を迎えるだろう。もう私にはどうでもいいことだった。
ブローカーを介して、私も“組織”に引き渡された。
お兄ちゃんの死を知ったのは、ちょうど“養成所”にはいるときだった。
多分私は、そのときから壊れてしまったのだろう。
現実から逃げ出すように必死に訓練に身を投じた。周りのものが見えない、自分のことも見えない、“心”なんて持たない、指示をこなすだけの“人形”。
そして夜になると、亡くなったお兄ちゃんのこと、自分がひとりになったこと、これから自分の両手が血に染まっていくことを考え、恐怖に震えながら朝までの長い時間を過ごすようになった。
それでも体は休息を求めるらしく、1日1時間は眠ることができた。調子がいいときは2時間。
しかし、そのわずかな睡眠も悪夢に妨げられることがほとんどだった。

そんな状態で1年が経ち、私は異例のはやさで“養成所”を卒業した。
そして――彼に会えた。
お兄ちゃんのパートナーだったそのひと。
一度“組織”を裏切った彼はちょうど“再教育”を終え、私とペアを組むことになった。
お兄ちゃんを殺した張本人である彼を、最初は憎むことにした。目を光らせ、全神経を尖らせて彼を監視した。
数日が経ち、張り詰めていた神経が限界を超えて切れたのか、それとも本能が“大丈夫”と判断したのか、ある日の任務のあと、私は彼のすぐそばで眠ってしまった。1年ぶりのぐっすりとした睡眠だった。
彼のそばは、お兄ちゃんと同じような安心感があったのだ。目が覚めた私は色んなことを思い出し、思わず泣いてしまった。
流した涙とともに心を縛り付けていた鎖が砕け散って、“人間の心”をようやく取り戻した気分だった。
泣きじゃくる私を彼は慌てて慰めようとしたが、結局、泣き声が大きくなるだけだった。
彼はお兄ちゃんの手紙に書いてある通りのひとだった。
無愛想で、ちょっと不器用で、けれど本当は深くパートナーを気遣うことができる、優しいひと。
“組織”に束縛され、殺しを強要され、それでも“人間”になることを諦めない、強いひと。
ただ、手紙のなかの彼よりも、大きな悲しみを背負っている。そんな彼が、自分が生き残るためにお兄ちゃんを裏切ったとは到底思えない。
手紙に残された最後の言葉から、真実は簡単に推測できた。
逃亡し、絶体絶命のピンチに陥ったお兄ちゃんと彼。
ふたりとも殺されるより、ひとりだけでも生き残ったほうがいい。
片方がもう片方を殺せば、それが可能だ。
だけどそんな提案をしても、きっと彼は認めないだろう。
認めたとしても、自分のほうが死ぬと言い出すにちがいない。
だからお兄ちゃんは彼を不意打ちし、彼を裏切るフリをした。
彼に自分を殺させることで、彼を生かした。
いちばん信じていたひとに裏切られたという大きな心の傷を与えて……ひどいひとだね、お兄ちゃんは。
それから、彼のそばが私にとっていちばん安心できる場所になった。
まるで1年分の睡眠を取り戻すかのように、昼間だろうと、任務中だろうと、機会があるたびに、私は彼のそばで眠った。
彼によく呆れられたものだ。しかし当の彼がいつも悪夢にうなされていたことを私は知っている。その原因のひとつに、お兄ちゃんとのことが大きく関わっているのだろう。
彼の苦しむ姿を見て、私は何度も彼に真実を告げようとした。
でもだめ! まだその時ではない!
彼は……演技が下手だったのだ。“養成所”でそういう訓練もあったから、別に動作や表情づくりが下手なわけではない。
ただ、変にまじめなところがあるせいか、度が過ぎたり、逆に足りなかったりすることがよくある。
勘の鋭い相手には簡単にバレてしまうのだ。きっと生まれつきひとを騙すのが苦手な性分なのだろう。だから、まだ彼に私のことを話すわけにはいかない。
彼はずっと前から逃走の準備をしていた。
仕方ないとはいえ、私に声を掛けてくれなかったのは少し寂しかった。
でも問題はそこではない。“組織”が彼を疑っていることこそが問題なのだ。
もちろん私は彼が不利になるような報告はしないけど、その心許ない演技が“組織”に見破られてしまえばどうしようもない。
まだ決定的な綻びになっていないはずだけど、それも時間の問題だろう。
ハルドル・バールン暗殺の報告を終えた際。私の目の前にいた男は、いつもとは明らかにちがう雰囲気を発していた。
その男こそ“管理人”――皇帝。私たちを管理し、人殺しを強制するいわゆる悪の親玉というやつだ。
いつもローブで顔を隠しているけど、その禍々しい気配までは隠しきれていない。
今のエンペラーは、まるで獲物を見つけた鷹のように静かに興奮している。
間違いない! エンペラーは彼の裏切りを確信している!
おそらくすぐにでも彼を殺すつもりだろう……それなら、こちらの作戦を実行するまで。私にお兄ちゃんのことを伝えたうえで彼と組ませたエンペラーの意図は明白だ。
私に復讐心を抱かせること、彼を嵌めて告発すること、彼にふたたび絶望を味あわせること、そして――自分がそれを観て楽しむこと。
私たちは“組織”の道具であると同時に、エンペラーのおもちゃでもあるのだ。
だったら望み通りにしてやる――
報告を終え、パートナーに叛意があることをエンペラーに伝える。
さらに私が場所と時間を指定し、彼を誘き出し、殺すまでの段取りをエンペラーに話し承諾を得る。
ローブの下に隠された顔は依然として見えないが、その言葉の端に漏れ出す愉悦の響きを私は聞き逃さなかった。
夕方、彼は私が指定した山奥の丘にやって来た。
突然の裏切りの告発に彼はひどく動揺し、さらにお兄ちゃんと私の関係を伝えたことで、その顔に驚愕と絶望と諦念が入り混じった。
彼のそんな表情を見ると私も悲しくなる。
それでも、嘲りと憎しみと殺意を込めた視線を彼に向け、悪意に満ちた言葉で彼の心を傷つける。
隣にいるエンペラーを騙すには、わずかの躊躇も許されない。
彼を攻撃するため、前に出る。
さらに鋼糸の攻撃を仕掛けるため、接近する。
だが本当の意図はエンペラーから距離を取ることにあった。
力ない反撃を受け流し、呆気なく彼に王手をかける。
鋼糸の輪が彼の首にかかり、勝負が決する。あとはほんの少し力を入れれば、彼の命が終わる。
指を動かし、声を上げる。
「これで、終わりよ」
演技ではない、本気の声。
普通の鋼糸のなかに混じった透明の糸が私の動きに応じ、収束する。
木々を伝い、遠くで複雑な幾何学模様を成した糸が瞬く間に輪を作り、その中心にいる獲物を縛り上げる。
――おもちゃが殺される瞬間を目に焼き付けようとして、周囲への警戒心が緩んだ状態のエンペラーを。
「ぐぅっっ――――」

最良のタイミングで仕掛けた不意打ちが見事にエンペラーを束縛した。
この透明色の糸は切断力がさほどあるわけではないが、この糸でなければ木々を伝うトリックも完成しなかった。
強度だけなら鋼糸の数倍はあるが、それでもエンペラー相手にいつまで持つか分からない。
すかさず私は用意したほかの糸を思い切り引く。
するとゴゴゴゴ……という低い音が響き、丘の岩が崩れはじめる。
前からこの辺りで岩盤が脆いところを探し、細工しておいたのだ。
落石が群れを成して転がり落ちる。なかにひとつ、直径10アージュを超える巨大な岩があった。
それが正確にエンペラーの頭上目掛けて “ズゴオオンッ” という轟音と地響きとともに、落下した。
落石が落ち着き、現場はまるで地震のあとのような惨状だった。
あんな質量の直撃を受けたエンペラーはさすがにもう生きてはいないだろう。死んでいないとしても、生き埋めだ。
隣にいた彼はまだ事態を理解できないのか、ポカンとした表情のまま立ち尽くしている。
「すーちゃん~~」
ようやく本来の呼びかたで彼を呼び、そして思いっきり彼の胸に飛び込む。
私がいちばん安心できる場所。頭をこすりつけたまま離れない。
ここまで甘えるのはさすがに初めてだ……だって、本当に怖かったんだから。
「色々ひどいこと言って、ごめんね……黙ってて、ごめんね……」
説明しなければいけないことはたくさんあるけど、とりあえずこれだけは伝えたかった。まだ状況を掴めていない彼は、それでも優しく私の頭を撫でてくれた。
「ナイン、一体どういう――」
その質問の言葉が終わらないうちに、異変が起きた。
落石の山がわずかに振動し、そして小さな石が、ゆっくりだけど――空中に浮かんだ。
「なっ!?」
目を瞠る私たち。
「空属性のアーツ? いや……」
それとはちがうような気がする……それとも飛行船と同じ飛翔機関だろうか?
わからない……思索を巡らしているなか、彼は厳しい声で言った。
「あれは、“管理人”の……エンペラーの能力だ!」
「えっ?」
思わず息をのむ。
それが意味するところは、エンペラーがまだ生きている、ということ。
そうしているうちに、さらに多くの石が浮かんでいく。
「逃げるぞ! ナイン!」
彼が呆然とした私の手を引き、走り出す。
かなりの距離を走ったあと、大きな爆発音につられて振り返る。
そこでは、まるで火山が噴火したかのように、巨大な岩が空高く噴き上がっていた……